〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A
JR津田沼駅から徒歩2分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分
月~金 | 9:30~19:30 |
|---|
土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |
|---|
費用は?管理義務から解放?
相続財産管理人選任の申立の流れや必要書類をわかりやすく解説!

人が亡くなったとき、遺された財産は通常であれば遺言書の内容や法定相続の配分に従って、相続人の間で分割されて受け渡されます。
しかし、はじめから相続人がいない場合や、
すべての相続人が相続放棄をしたため結果的に相続人がいなくなる場合もあります。
そういった場合でも、亡くなった人の財産を持ち主不在のまま放置するわけにもいきません。
日本で亡くなった方の相続財産の総額は、年間約50兆円にも及びます。これは、韓国の国家予算(2022年予算案は約57兆4,180億円)にも匹敵するほどの巨大な数字です。
そこで、相続人がいない遺産の管理・清算のために、第三者から「相続財産管理人」を選任することになります。
これから相続放棄をしようと考えている方は、相続財産管理人の選任申立をする必要が出てくる可能性もあります。
典型例は、空き家があり、倒壊等の不動産管理上のリスクを回避するため、
つまり不動産管理義務から解放するために相続財産管理人を選任申立するケースです。
ここでは、相続財産管理人の役割と、実際に選任の申立てを行う手続きの流れを詳しく解説していきます。もあります。
目次
1.管理すべき財産があるが、
相続人全員が相続放棄した場合
2.特別縁故者がいる場合
3.被相続人に債務(借金)がある場合
・必要書類
・申立~審判
・相続財産管理人報酬
①相続人がいないと故人の財産はどうなる?
相続人がいない・あるいは相続人全員が相続放棄をした場合の故人の財産は、最終的には国庫に帰属すると定められています(民法959条)。
ちなみに、国庫に帰属する金額は、毎年440億円にも及ぶ(2016年)と言われています。
しかし、相続人がいなければ必ずしも自動的にすべての財産が国のものになるというわけではありません。
たとえば、故人に債務があった場合は、遺産から債権者に支払われます。
また、内縁の配偶者や世話をしていた人等、相続人ではないけれども特別な関係にあった人(特別縁故者といいます)がいた場合は、その人に財産分与が行われることもあります。
このような清算を経て、最終的に残った財産は国のものとなるわけですが、相続人がいない以上誰かが代わりにこれらの手続きを行わなくてはなりません。
そのために選任されるのが相続財産管理人です。
②相続財産管理人の選任申立は誰が行う?
3つのケース
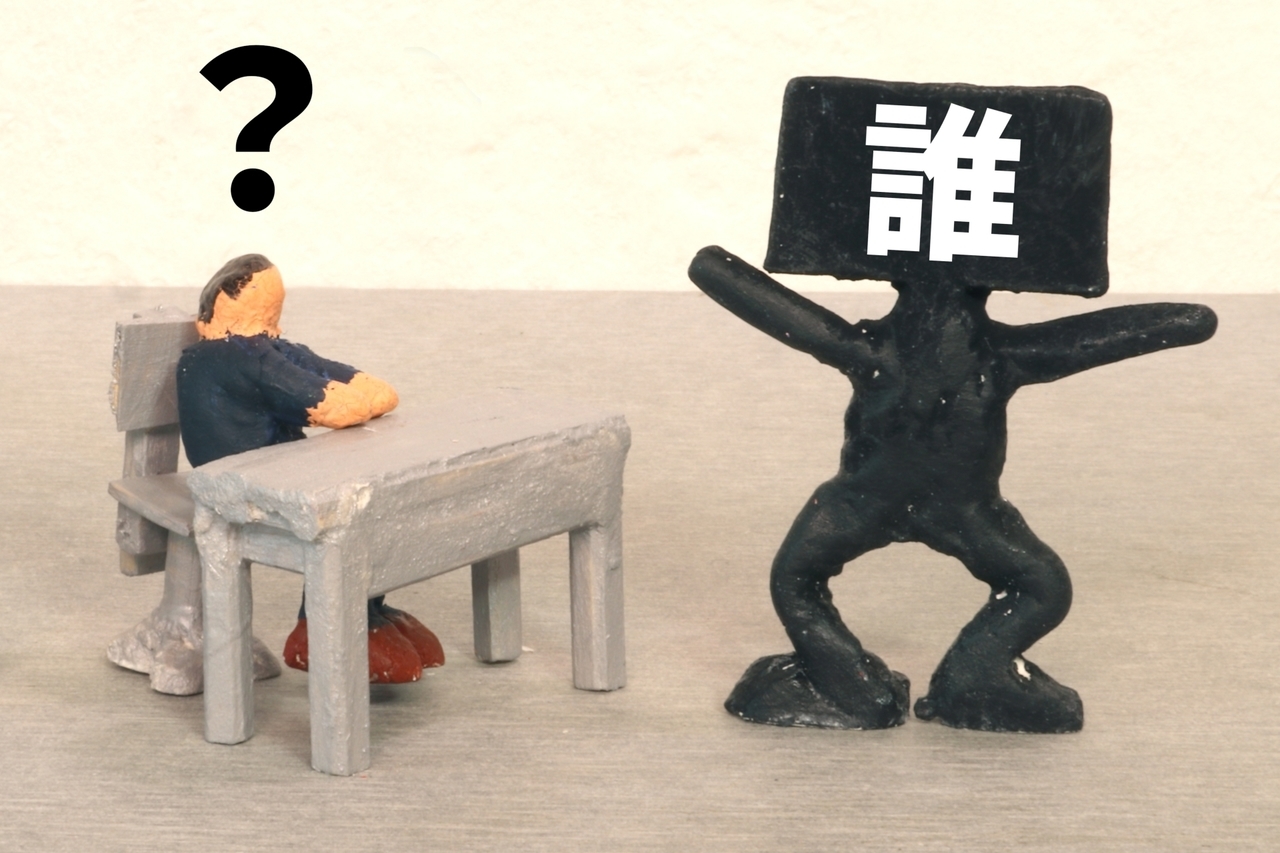
1.管理すべき財産があるが、
相続人全員が相続放棄した場合
この場合、相続放棄をした人が相続財産管理人の選任申立をします。
故人が土地や家屋などの不動産を所有していた場合、相続する人がいなければ、誰かが管理をしなくてはいけません。
場合によっては、相続放棄をしたとしても、財産の保存義務は残る可能性があります。
(詳しくはこちらの記事でも解説しています。令和5年施行!相続放棄と管理責任の法改正を司法書士がわかりやすく解説! )
そうすると、相続放棄をしたにもかかわらず、他に相続人がいなければ、財産の管理を続けなくてはならなくなります。
このような場合、相続放棄をした人が勝手に財産を処分や売却することはできませんので、代わりに相続財産管理人を選任し、清算する必要があります。
2.特別縁故者がいる場合
民法958条の3
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
民法において、被相続人の「生計を同じくしていた者」「療養看護に努めた者」「特別の縁故があった者」に対し、相続財産の分与が認められています。
内縁の配偶者や身の回りの世話や介護を手厚く行っていた人に対しては一定の財産が与えられるというわけです。
なお、特別縁故者への財産分与は、相続人がいないことが大前提である点に注意です。
とはいえ、もちろん裁判所の許可なく勝手に財産を持っていくことはできませんので、相続財産管理人を選任して、相続人がいないことも確認した上で財産分与の手続きを行ってもらうことになります。
3.被相続人に債務(借金)があった場合
被相続人に債務があった場合、通常では相続人が相続財産の中から支払いに充てますが、相続人がいない場合、債権者が請求する先がありません。
そのため、債権者が相続財産管理人の選任申立を行い、場合によっては相続財産管理人が被相続人の不動産や証券を金銭に換え、債権者への支払いに充てることになります。
③相続財産管理人の選任申立の流れ
必要書類
相続人財産管理人の選任申立は、家庭裁判所に対して行います。
まずは家庭裁判所に提出する必要書類を集めます。
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
②法定相続人がいない(亡くなっている)ことがわかる戸籍全て
具体的には、
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
③被相続人の住民票除票又は戸籍附票
④財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
⑤利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
⑥相続財産管理人の候補者がある場合、その住民票又は戸籍附票
⑦申立書
裁判所ホームページよりダウンロードできる家事審判申立書に記入をします。
事件名の枠に「相続人財産管理人選任」と記載し、下の必要事項を全て記入しましょう。
また、1件あたり800円の手数料が必要です。収入印紙で申立書に貼ります。
⑧連絡用の郵便切手
申し立てをする裁判所によって金額が異なります。問い合わせをして確認しましょう。
申立~審判
上記の書類を揃えたら、
被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
問題なく受理されると、裁判所によって審理が開始します。
場合によっては、状況を判断するための必要書類の追加提出を求められることもあります。また、直接状況を聞くために裁判所から呼び出しをされることもあります。
この審理の結果によって、申立人に「審判書」が送られます。
申立が認められた場合、審判書には、裁判所が選任した相続財産管理人の氏名と住所などが記載されています。
また、相続財産管理人が選任されると、その事実が官報に載りますので、官報公告費用として3,775円を納めます。裁判所から送られる納入用紙にて納入します。
相続財産管理人の報酬
相続財産管理人の報酬は、原則として相続財産の中から支払われますが、予納金が必要になる場合があります。
申立人が相続財産管理人への報酬として予納金を納め、相続財産から報酬の支払いができる場合には予納金は返ってきますが、相続財産が少ない場合など報酬額に足りなければ、予納金から支払われることになります。
予納金の額は、状況によって家庭裁判所が決定しますが、事案によっては数十万を超える予納金が必要になることもあります。
目安として、例えば東京家庭裁判所では原則100万円、他の裁判所では30~60万円程度になることが多いです。
事案によっては、予納金の返還が見込まれず申立人にとって大きな負担になることもありますので、慎重に判断する必要があります。
私見ですが、相続財産管理人の選任申立をする人が少ない最大の理由は、予納金が高額であることであると思われます。
このように、相続財産管理人が必要になるケースというのは状況が難しく、手続きも煩雑になりがちです。
専門家に依頼をすれば、書類の収集から申立てのサポートまでほぼ全てを任せることができます。
まずは、一度当事務所(船橋市・習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~19:30
事前予約で時間外・土日、祝日に面談可
定休日 なし
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
津田沼・千葉相続相談室

住所
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A
アクセス
JR津田沼駅から徒歩2分
京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分
受付時間
平日 9:30~19:30
営業時間外・土日、祝日対応可
定休日
なし

