公正証書遺言の書き方
・手続きの流れを解説
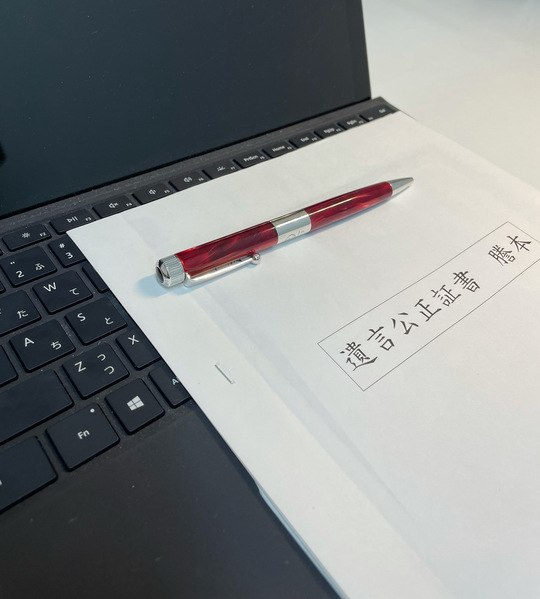
遺言書には、大きく分けて
遺言者が手書きで作成する「自筆証書遺言」、
証人の立ち合いのもと公証役場で作成する「公正証書遺言」、
誰にも見られずに作成できる「秘密証書遺言」
の三種類があります。
公正証書遺言は、その中でも最も確実性が高い方法で、利用する方も年々増加傾向にあります。
しかし、確実である分、作成には少し時間がかかり、自筆証書遺言よりは手続きも複雑な面があります。
ここでは公正証書遺言の特性、書き方をわかりやすく解説していきます。
①公正証書遺言とは
公正証書遺言は、
・遺言者
・公証人
・二人以上の証人
が 公証役場で作成する遺言書のことです。
遺言を公証人が書面化し読み上げ、証人はそこに誤りがないことを確認する
という流れで作成されます。
公証人という専門家が書面化するため不備の可能性がとても低いこと
作成後は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、または死後発見されないといった懸念がないこと
が特徴です。こういった点から、有効性の高い遺言を作成したいとお考えの方には特にお勧めの方法です。
②公正証書遺言の書き方・
手続きの流れ(6ステップ)
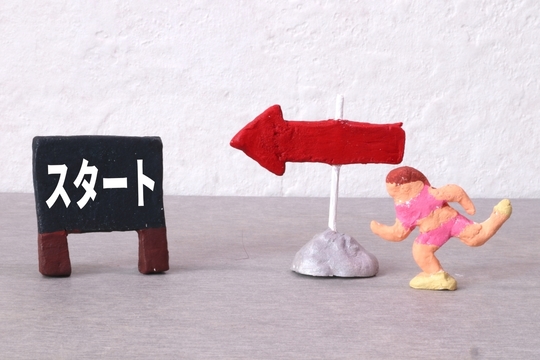
以下が公正証書遺言作成の6つのステップです。
① 遺言書の内容を決める
まずは、遺言書の内容を決めるために、財産を「誰に、どれだけ」相続させるかを決めていきます。そのためにすべての財産と相続人を洗い出すことから始めます。
この作業は、他の方式の遺言書でも同様に初めに行うことになります。
財産と相続人を洗い出したら、誰に何をどれだけ相続させるかということを書き出していきますが、ここで作るのはまだ遺言書の叩き台ですので、書式等は気にせず、箇条書きで書き出しておくくらいで 大丈夫です。
↓
② 立ち会ってもらう証人を2人決める
公正証書遺言の作成時には必ず二名の証人が立ち会います。
この証人は遺言者が自由に選任することができますが、
・未成年者
・推定相続人、及びその配偶者、直系血族、遺言によって利害を受ける人
は証人になることができません。
ご自身で証人となる人を選ぶのが難しい場合は、司法書士等の専門家に依頼をすることもできます。
また、公証役場に相談をして、証人を紹介してもらうこともできます。
↓
③ 必要書類を集める
公証役場で手続きをするために必要な書類を集めます。
・相続人との関係が分かる戸籍謄本
・財産資料(通帳のコピー、不動産の登記簿謄本等)
この二点は、①の作業の際に集めておくとよいでしょう。
・印鑑証明書(作成後3か月以内)
・身分証明書(免許証等)
・(相続人以外に財産を渡したい場合)受遺者の住民票
以上の書類を集めたら、次は公証役場に連絡します。
なお、上記の書類があればそれに越したことはありませんが、ないと絶対に作成ができないわけではありません。
これらの書類のほかに、作成当日は手数料が必要です。
【公証役場手数料】
手数料は財産の額によって異なり、
100万円以下 5000円
100万円を超えて200万円まで 7000円
200万円を超えて500万円まで 11000円
500万円を超えて1000万円まで 17000円
1000万円を超えて3000万円まで 23000円
3000万円を超えて5000万円まで 29000円
5000万円を超えて1億円まで 43000円
1億円を超えて3億円まで 43000円+超過額5000万円までごとに13000円を加算
3億円を超えて10億円まで 95000円+超過額5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円+超過額5000万円までごとに8000円を加算
となります。
財産の総額ではなく、相続人一人あたりについての額でそれぞれ算出され、合算した額が手数料となります。
↓
④ 公証役場に予約を取る
手元に必要書類が準備できたら、公証役場に公正証書遺言作成の申し入れをします。
公証役場一覧 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)(日本公証人連合会ホームページより引用)
公証役場のホームページからお近くの公証役場を調べ、電話をかけます。
「公正証書遺言を作成したい」旨を伝えれば大丈夫です。
案内に従って書類を提出し、その後のスケジュールを設定しましょう。
↓
⑤ 遺言内容の打ち合わせ
遺言内容によっては、公証人との事前打ち合わせが必要になる場合があります。
内容によっては複数回行うこともあります。期間は2週間から一か月程度かかることが多いですが、経験上、公証人が混雑していると、2か月以上待つことも珍しくありません。
①で作成した叩き台を元に、公証人と相談しながら遺言書の書案を作っていきます。
なお、注意が必要なのは、公証人が相談に応じてくれるのは財産目録の正確性等、法的な不備がないかという点で、遺言書の内容そのもの(誰に相続させたいか)については基本的に助言されません。
そもそもの遺言内容について不安がある場合には①の段階で専門家に相談するとよいでしょう。
↓
⑥ 遺言書作成日当日
当日は証人二人とともに公証役場に行き、遺言書を確認します。
ちなみに、身体的理由等で公証役場に行くのが難しい場合は、公証人が出張してくれることもあります。別途出張費が発生しますが、あらかじめ可能かどうか確認しておきましょう。
遺言者の本人確認が終わったら、公証人が書いた書案を読み上げるので、遺言者は内容に齟齬がないか確認し、証人はそれらが正しく行われたことを承認します。
問題がなければ遺言者、証人が遺言書に署名、押印し、その後公証人が署名、押印すれば完成です。
作成した遺言書の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に渡されます。
以上で公正証書遺言の作成は完了です。
③まとめ
公正証書遺言の作成は、上記の流れのとおりですが、
当事務所の遺言書作成サポートでは、遺言内容のご希望だけお伝えしてしていただければ、公証人とのやり取りはすべて司法書士が代行しますので、遺言書を作成される方には何もしていただくことはありません。
また、法的アドバイスも一緒にできますので、安心して確実な遺言書を作ることができます。
まずは、一度当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
