行方不明者、不在者、失踪者
がいるときの相続方法を
司法書士がわかりやすく解説!
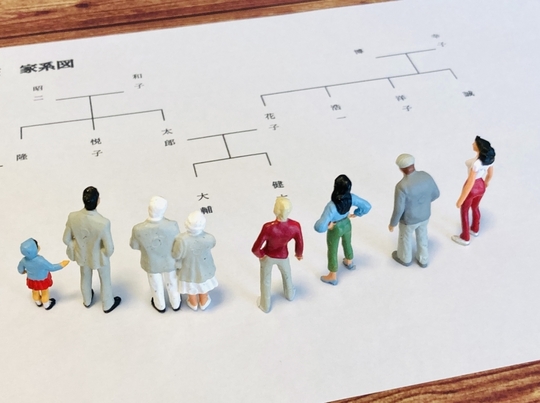
遺産分割は、必ず相続人全員で行わなくてはなりません。何年も連絡をとっていない親族などがいると連絡先を調べるだけでも一苦労です。
では、もし、相続人の中に生死不明な人、行方不明者がいる場合はどうすればよいのでしょうか。
行方不明であっても相続人として扱われますので、遺産分割協議に参加できなければ相続手続きを進めることができなくなってしまいます。
ここでは、相続人の中に行方不明者、失踪者がいる場合の対応方法を具体的に説明します。
目次
・不在者財産管理人とは
・不在者財産管理人になれる人
・不在者財産管理人の仕事
・不在者財産管理人の任期
・普通失踪
・特別失踪
①存在を知らなかった相続人や
長年にわたり疎遠な相続人がいる場合
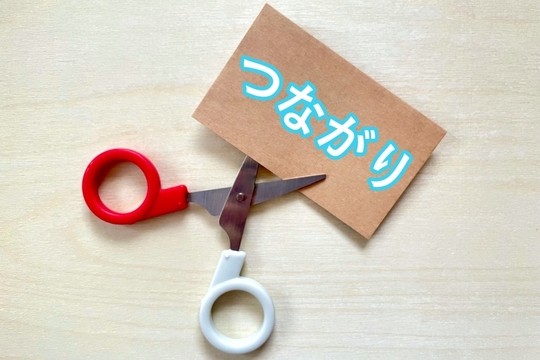
相続手続きにおいて、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることから始めますが、その中で予期せぬ相続人の存在が判明することがあります。
被相続人が過去に認知をした子供
被相続人と疎遠な兄弟・およびその兄弟が亡くなっていた場合の子供
などがよくある事例です。
この場合は、行方不明というのとは異なりますが、相続人の現在の所在が分からない状況ではありますので、まずは生死と現住所を調べ、こちらから連絡をとる必要があります。
役所で戸籍附票を取得し、住居を調べて手紙でコンタクトをとる方法が一般的です。
こういった状況での調査の仕方、連絡方法などはこちらの記事でより詳しく解説しています。ご参照ください。
②行方不明の場合→不在者財産管理人
(戸籍を調べても相続人の所在が不明)

戸籍の附票を取得しても実際にはその住所に住んでいない等、完全に所在を知ることができない時は、その相続人本人がいないまま相続手続きを進めなければなりません。
しかし、遺産分割は相続人全員で行わなければならないため、所在が分からない相続人(不在者)の代理を立てて遺産分割協議を行うことになります。
その代理人を不在者財産管理人といいます。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人は、その名の通り不在者に代わってその人が本来得られるべき財産を管理してくれる人です。
家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任の申し立てを行うことで決められます。
不在者財産管理人になれる人
不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議に参加しますので、他の相続人と利害関係がある人がなることは出来ません。特定の相続人が得をするような不平等が起こりかねないからです。
よって、不在者財産管理人は相続に利害関係のない第三者を選任する必要があります。親族等で適任の人がいない場合には、司法書士、弁護士等の専門家が選任されます。
不在者財産管理人の仕事
不在者財産管理人が行うことは、遺産分割協議のみではありません。相続後の不在者の財産管理も引き続き不在者財産管理人の仕事です。選任の際には、必ずこのことを考慮しなくてはなりません。
具体的には、不在者の財産を財産目録にまとめて家庭裁判所に定期的に提出します。また、不在者が債務を抱えている場合は、財産の中から精算を行うこともあります。
不在者財産管理人の任期
不在者財産管理人の仕事が終わるのは、以下の三つの場合です。
①不在者が見つかったとき
不在者の所在が判明した時は、不在者の財産はそのまま本人に受け渡されます。
②不在者の死亡が明らかになったとき
不在者が死亡していることが判明した場合は、不在者が被相続人となる相続手続きに移行します。
③不在者の失踪宣告が裁判所に認められたとき
失踪宣告については以下の項目で詳しく解説します。
③長期間行方不明の場合→失踪宣告
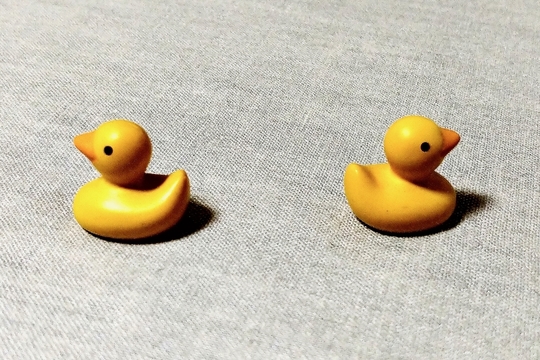
失踪宣告とは(普通失踪)
行方不明になり、生死不明の状態が7年以上続いている場合は、裁判所から失踪宣告の申立をすることが出来ます。
これは、長期間の生死不明状態が続いている行方不明者に対して、「死亡したものとみなす」という判断をする宣告です。
民法31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
普通失踪は、7年以上生死不明の場合のことで、
特別失踪は、戦争や災害、船が沈没したような場合のことです。
失踪宣告によって、不在者が相続人であるならば、不在者は死亡しているという扱いになり他の相続人のみで遺産分割協議を行うことになります。
失踪宣告には、
家庭裁判所への資料提出・失踪宣告の申立て→調査→審判
という手順を踏むことになりますが、本来生きているかもしれない人を死亡扱いとする繊細な手続きですので、申立ても簡単ではなく、期間もかかります(通常、一年ほど要することが多いです)。
失踪宣告の申立をすることができるのは、「利害関係人」です。他方、不在者財産管理人の申立は「利害関係人または検察官」ができます。
ちなみにですが、失踪宣告の申立権者に検察官が含まれていないのは、公益の代表者である検察官(イメージは国家側の人間)が個人を死亡したものとみなす制度を利用できるのは問題があるからだと思われます(私見)。
失踪宣告を検討されている場合には、専門家に相談して行うことをお勧めします。
特別失踪とは
行方不明から7年が経過していなくても失踪宣告が認められる場合があります。
海難事故、地震や洪水などの自然災害、戦争等で行方が分からなくなった場合です。
このような場合、それらの危難に遭った時点から行方不明が続いていれば、死亡している可能性が高いとみなされ、危難に遭った時点から1年経てば危難失踪の申立てが可能になります。
正確には、「危難が去った時」から1年間生死が明らかでない場合、と定められています。
なお、死亡したとみなされる時期は、「危難が去った時」です。(1年後ではありません)
危難失踪の申立ても通常の失踪宣告と同様、家庭裁判所に対し書類を提出して行います。
④まとめ
行方不明者がいる場合の相続手続きは、
・不在者財産管理人という代理を立てての遺産分割協議
・失踪宣告によって不在者を死亡しているとみなしての手続き
の、大きく分けて2つの方法で開始することになります。
【勘違いしやすいポイント】
生死不明が7年以上の場合は、必ずしも失踪宣告を選択しないといけないわけではなく、不在者財産管理人の申立要件を満たしていれば、そちらを選択することも可能です。
両者は、要件や期間、費用(特に裁判所に納める予納金)が大きく変わるため、個別的な事情に応じてどちらを選択すべきかの判断が非常に重要です。
通常の相続手続きよりもさらに煩雑で時間がかかる手続きになることが予想されますので、専門家の力を借りて行うのがよいでしょう。
まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。船橋市・習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
