土地が8割引!?
絶対使うべき
小規模宅地特定の要件とは?

土地にかかる相続税を大幅に減額できる可能性がある、小規模宅地等の特例についてご紹介します。
1.小規模宅地等の特例とは?
例えば、被相続人(亡くなった人)の不動産に、相続人となる家族が同居していた場合、もしもその不動産の相続に多額の相続税が発生したら、その場所に住み続けることができなくなってしまう可能性があります。そういった事態を避けるため、主に被相続人の同居親族が相続した自宅に住み続ける場合などに、相続税の負担を大幅に軽減できる制度があります。それがこの小規模宅地等の特例です。
最大で80%もの減額ができる場合もありますので、相続税を減額したいと思ったら絶対に利用すべき制度です。
〇対象となる土地
この小規模宅地等の特例が適用される土地は、大きく分けて三種類あります。
・実際に住んでいた土地(特定居住用宅地等)
・事業をしていた土地(特定事業用宅地等)
・貸していた土地(貸付事業用宅地等)
これらの土地の、相続するにあたっての評価額を大幅に減額してくれる制度が小規模宅地等の特例です。
相続税が課税される土地の価格は、地域ごとに国税庁によって定められています。この価格を路線価といいます。
例えば300㎡の土地を所有していて、路線価(1㎡あたり)が20万円の場合、6000万円が相続税評価額になります。
ここから小規模宅地等の特例を適用した場合、以下のように土地の相続税評価額を減額することができます。
実際に住んでいた土地→330㎡まで、80%の減額
事業をしていた土地→400㎡まで、80%の減額
貸していた土地→200㎡まで、50%の減額
つまり上記の例の6000万円の相続税評価額の土地に居住していた場合であれば、要件を満たしていれば、土地の相続税評価額を1200万円まで減額することができます。
それぞれの土地について、具体的な適用条件について紹介していきます。
2.実際に住んでいた土地
(特定居住用宅地等)
被相続人となる故人が住宅として使用していた土地の場合、小規模宅地等の特例を適用できる相続人の範囲は以下のように分けられます。
ⅰ配偶者
被相続人の配偶者がその土地を取得する場合は、配偶者がその土地に住んでいなかったとしても、無条件で小規模宅地等の特例が適用できます。
ⅱ同居親族
被相続人と生前から同居していた親族が土地を取得する場合には、被相続人の死亡後もその土地に住み続けるという条件付きで特例の適用対象になります。具体的には、被相続人の死亡後10ヶ月までその土地に居住していれば、小規模宅地等の特例が適用できます。
ⅲ別居の親族(家なき子特例)
被相続人と同居していなかった親族であっても、要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用できます。ざっくりと言うと、被相続人と別居であり、自己所有の家を持っていない親族(実家を出て賃貸物件で暮らす子供等)が対象になります。
要 件
・ⅰ、ⅱに該当する者(被相続人の配偶者、同居の親族)がいないこと。
・相続開始の3年以内に自己が所有する家・3親等以内の親族、及び親族が経営する法人が所有する家に住んだことがないこと。
・相続開始時に住んでいる家を過去に一度でも所有したことがないこと。
そしてⅱの場合同様、
・被相続人の死亡後10ヶ月までその土地に居住していること。
以上の全ての要件を満たしていれば、別居親族でも小規模宅地等の特例を受けることができます。
3.事業をしていた土地
(特定事業用宅地等)
被相続人が自己の所有する土地で事業を行っており、被相続人の死亡後もその事業を継続する場合、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することができます。
この貸付事業用宅地等について、平成31年度に税制の改正がありました。
相続開始前3年以内に事業用として供された不動産に関しては、小規模宅地等の特例が適用されない(例外あり)
というものです。
ですので、特定事業用宅地等については、
・被相続人が亡くなる3年以上前からその土地で事業を営んでいる
・相続人が相続税の申告期限までその事業を継続していること
のどちらも満たしていることが適用の要件になります。
4.貸していた土地
(貸付事業用宅地等)
被相続人が所有する土地で、例えば、賃貸物件や貸駐車場として貸し付けをしていた場合も、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することができます。
この貸付事業用宅地等についても、平成30年度に税制の改正により
相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産に関しては、小規模宅地等の特例が適用されない
と定められています。
また、便宜上貸付事業用としているものの実態を伴っていない等の場合も、適用外となる可能性があります。
・被相続人が亡くなる3年以上前からその土地で不動産貸付を行っていること
・相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付を継続していること
のどちらも満たしていることが適用の要件になります。
5.小規模宅地等の特例を
適用するための手続き
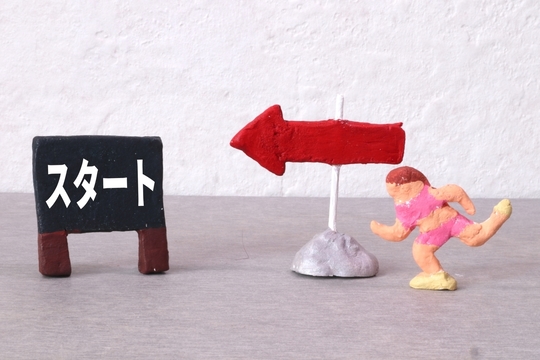
ここまでで紹介した要件を満たしている場合でも、自動的に土地の相続税評価額を減額してもらえるわけではありません。この特例を適用するためには、各種必要書類を集め、管轄税務署へ申告する必要があります。
書類のうち、「必ず必要なもの」は
・相続税の申告書
・被相続人の全ての相続人が記載されている戸籍の謄本、
または法定相続情報一覧図
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書の写し、
または遺産分割協議書の写し
があります。
この他に土地の種類や、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの状況によって別途追加で必要になるものがあります。
6.まとめ
以上のように、この小規模宅地等の特例は、要件を満たしていれば相続税対策の方法の中でもかなり大幅な減額が期待できるものです。その分、特例が適用できるかどうかの判断や準備についてはしっかりと備えていきたいところです。判断に迷う場合や不安がある場合には、専門家への相談もおすすめです。
