任意後見制度の利用方法
・手続きの流れ

①任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、判断能力が衰えたとき(ex.認知症など)に備えて、まだ判断能力がある段階で後見人の候補者を選んでおく制度です。
法定後見制度との違い
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した後になされる手続きです。本人の判断能力が衰えた後ですから、任意後見と違い、自分で後見人候補者を選ぶことができません。
②任意後見のメリット・デメリット
メリット
① 後見人候補者を自分で選ぶことができる
② 後見監督人が必ず選任され、監督してもらえる
③ 自由に制度設計できる(重要!)
【解説】
① 後見人となる人(候補者)をあらかじめ自分が信頼できる人に指定することができます。他方、法定 後見では、裁判所が選任権限を持つため、誰が選任されるかはわかりません。
② 後見監督人とは、後見人がしっかりと任務を遂行しているか(財産を適切に管理しているか、横領していないかなど)、後見人を監督する人のことです。法定後見と違い、任意後見では必ず監督人が選任されるため安心です。
③ 本人の希望通りの制度設計ができます。
例えば、自分の希望する人を後見人に選ぶことや、後見人の報酬も自由に決められます。
また、契約内容も自由に決められるので、将来どの病院・介護施設に入れてほしいかなど、細かな要望を決めておくことが可能です。
デメリット
① 死後の事務処理や財産管理を委任することはできない
② 後見人には取消権がない
③ 手続きが少し大変
【解説】
① 本人が亡くなった後の事務処理(葬儀、お墓、片付け、遺品整理など)を後見人に委託することはできません。理由は、後見は本人の死亡によって終了するからです。この点は法定後見と同様です。
これらの事務処理も委託したい場合、別途死後事務処理委任契約を締結しておく必要があります。言い換えると、任意後見契約と死後事務処理委任契約もセットでしておくと、万全です。
② 法定後見と違い、任意後見人には取消権がありません。
そのため、本人が特殊詐欺や訪問販売詐欺に遭った場合などでも、後見人が契約の取り消しをすることができません。この点は、本人の財産保護の観点からは少々不安要素となります。
③ 任意後見契約の場合、以下「③任意後見手続きの全体的な流れ」にあるように、公証役場で公正証書作成、裁判所への申立てなどが必要なため、その分時間と費用(主に専門家費用)がかかります。
③任意後見手続きの全体的な流れ
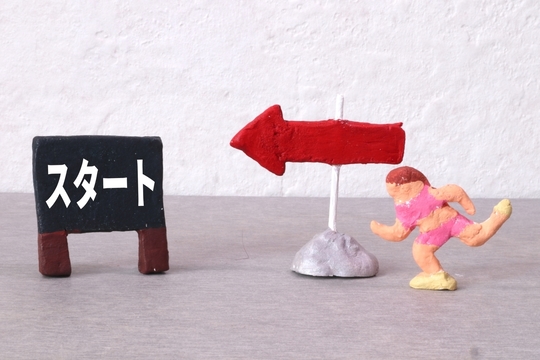
以下が任意後見制度の流れです。
①②③は、任意後見契約を締結するまでの流れ、
④⑤は、判断能力が衰えた後の流れです。
① まず、任意後見受任者(後見人になってくれる候補の人)を決めます。
ご家族や信頼できるご友人などを候補者にすることができます。
また、後見人になるには、以下の欠格事由にあたらない限り、資格は特に必要ありません。
そのため、法人も後見人になれますし、後見人を複数つけることも可能です。
【欠格事由】(民法847条参照)
・未成年者
・破産者
・行方不明者
・家裁で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
(=家裁から法定代理人を解任されたような場合)
・被後見人に対して訴訟をしている、またはした者並びにその配偶者、直系血族
(理由 本人と裁判した人やその親族は、一般に関係性がよくないため)
↓
② 次に、契約内容を決めます。
自由に契約内容を決めることができます。例えば、病院はこの病院にしてほしい、施設は家から近い〇〇施設に入りたい、などです。
【注意事項】
任意後見契約だけではカバーできない部分もございます。
①介護、身の回りの世話、ペットの世話など
これらは任意後見契約の範囲外ですので、これらも委任したい場合は別途委任契約を結んでおきましょう。
②死後の事務処理
これらも任意後見契約の範囲外のため、別途委任契約が必要です。
↓
③ 契約内容が決まれば、公正証書にする
任意後見契約は必ず公正証書にする必要があり、公正証書によらない場合は無効です。
近くの公証役場に行きましょう。
約15,000円~20,000円程度の実費代がかかります。
↓
④ 判断能力が低下した後、任意後見監督人の申立てを行う
認知症が進行するなど、判断能力が衰えた後は、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
任意後見監督人が選任されることによって初めて任意後見の効力が発生します。
申立ては、「本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者(任意後見人の候補になった人)」がすることができます。
↓
⑤ 任意後見受任者が任意後見人になり、後見がスタートする
④任意後見には3つのタピプがある
任意後見の3つのタイプ
① 将来型
② 移行型
③ 即効型
①将来型
まだ本人に判断能力が十分あるうちに、任意後見契約を締結しておくタイプです。
【デメリット】
任意後見契約から任意後見開始(=判断能力が衰える)までに結構時間が経つことがあり、判断能力が低下した事実に気が付かない可能性があります。
【対策】
定期的に連絡をいれるなど、本人の状態を見守る「見守り契約」をしておくとよいでしょう。
②移行型
手続きとしては、任意後見契約と財産管理に関する委任契約を一緒に結んでおきます。
任意後見契約が開始(=判断能力が低下)する前に、まず財産管理に関する委任契約を開始しておき、その後、判断能力が低下したときに、任意後見へ「移行」するタイプです。
【メリット】
ひとまず、財産管理に関する委任契約がスタートしており、本人と接触する機会があるため、将来型のような、本人の判断能力が低下した事実に気が付かない、といったリスクを減らすことができます。
③即効型
任意後見契約締結と同時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立てを行い、任意後見を直ちに開始するタイプです。
即効型は、「本人の判断能力がすでに低下しているが、任意後見契約を締結する判断能力はまだ持っている状態」にできます。※完全に判断能力がないと、任意後見契約自体ができず無効になります。
【デメリット】
すでに判断能力が低下していることから、判断能力の鑑定に時間を要したり、判断能力がなかったとして任意後見契約自体が無効になるリスクがあります。
⑤まとめ
任意後見手続きは、やや手続きが複雑ですが、いくつかの契約を適切に組み合わせて使うことによって、使い勝手のよい制度でもあります。
判断能力が完全になくなってしまってからでは手続きできませんので、まだお元気なうちに、終活の一つとしてされるとよいと思います。
まずは、一度当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
