外国籍や海外在住・行方不明の
相続人がいる場合の相続手続を
司法書士が解説!
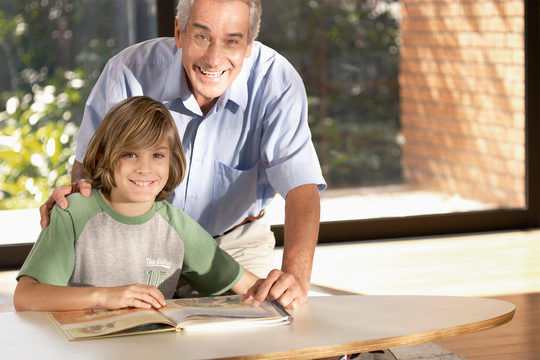
近年、相続人の中に海外在住の方がいらっしゃるケースのご相談をいただくことが増えています。
海外に在住していても、法定相続人であれば、必ず遺産分割協議に参加しなくてはならないことに変わりはありません。
とはいえ、日頃から連絡を取り合っている家族であればまだしも、海外に住んでいる相続人が疎遠な相手であればなかなか簡単ではありません。時には被相続人が亡くなって、いざ相続人の調査をした時に初めて海外に知らない相続人がいることを知る、という事態も実際に起こっているケースです。
そのような場合はまず何からしたらよいかと悩んでしまうかと思います。
ここでは 被相続人が日本国籍で、相続人の中に外国籍、または海外在住の方がいるケースについて解説しています。
日本国内のみで完結する相続と比べ、必要な書類や手続きが一部異なったり、増えたりしていますので、注意して準備をしていきましょう。
目次
- 海外に相続人がいる場合の相続手続(概要)
- まずは所在調査から
- ①所在確認
- ②それでも所在がわからない場合は
- 1.外務省の所在調査
- 2.行方不明者・失踪者としての手続き
- 相続人と連絡が取れたら遺産分割協議書を作成
- 必要書類の取得(在留証明書等)
- ①署名証明書(サイン証明書)
- ②在留証明書
- ③宣誓供述書
- ④台湾在住(相続人が日本国籍)の場合
海外に相続人がいる場合の相続手続(概要)
まず、前提として、相続は「被相続人の本国法による」と定められています。
つまり亡くなった方(被相続人)が日本国籍であれば、相続人が海外に在住していたり、外国籍を取得していたりしたとしても、日本の法律に拠って相続手続きを行います。
※逆に言うと、被相続人が外国籍の場合は手続きや必要書類が大きく変わります。
ですので、戸籍から相続人の全員を調査し、全員で遺産分割協議を行い、その結果に従って遺産を分配して相続する、という基本的な流れは通常の相続と同じです。
もしも海外在住の相続人を含めずに遺産分割協議をしてしまうと、無効になりやり直さなくてはなりませんので、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍をくまなく調査し、相続人全員を洗い出しましょう(法定相続人の範囲についてはこちらでも詳しく解説しています。
まずは所在調査から

①所在確認
海外在住の相続人がいることがわかったら、まずは何らかの方法で相続が発生したこと、遺産分割協議への参加が必要であることを伝えなければなりません。
連絡先を知っているならば、そのまま連絡をすればよいのですが、長年疎遠で連絡先を知らない、または知っている住所に書面を送っても宛先不明で戻ってきてしまった、となると調査が必要になります。
住民票を海外に移していると、戸籍の附票を取得しても、例えば「アメリカ合衆国●●州」のような記載しかなく、詳細な住所は書かれていません。
親族でその人物の連絡先を知っていそうな人とコンタクトを取り、事情を説明した上で連絡を取ってもらうなど、まずはできる限りの調査を試みます。
②それでも所在がわからない場合は
1.外務省の所在調査
あまり知られていませんが、外務省に所在調査をすることができます。
ただし、申請には
・被調査人(所在不明者)が日本国籍を所持していること
(婚姻等で外国籍を取得していると調査できない)
・依頼者から三親等以内の親族であること
という条件があります。
2.行方不明者・失踪者としての手続
それでも見つからない場合・それ以上調査ができないという場合になると、不在者財産管理人選任申立、失踪宣告などの手続きが必要となります。
(相続人の中に行方不明者、不在者、失踪者がいる時の相続方法についてはこちらをご参照ください→行方不明者、不在者、失踪者がいるときの相続方法を司法書士がわかりやすく解説! )
ここまでくると、相続が発生し、ただでさえ他にもやることが多い中、個人での手続きは負担が大きくなってくるかもしれません。難しいと思ったらまずは一度専門家に相談することをお勧めします。
相続人と連絡が取れたら遺産分割協議書を作成
相続人全員と連絡が取れたら、全員で遺産分割協議を行います。これについては通常の相続と同じです。
協議に関しては対面に限らず、メール等でのやり取りでも構いませんので、国内での遺産分割協議とあまり変わらず行えるかと思います。
必要書類の取得(在留証明書等)
①署名証明書(サイン証明書)
遺産分割協議書には最終的に相続人全員の署名捺印と、印鑑証明書の提出が必要です。
しかし、海外に在住していると、韓国、台湾を除き、ほとんどの国では印鑑登録制度がありませんので、印鑑証明書の代わりとなる書類が必要となります。
その場合、海外在住の相続人本人が、署名証明書を申請する必要があります。
署名証明の申請は、
・日本国籍の場合→日本国大使館等、現地の在外公館
・外国籍の場合→現地の公証人
に対し行います。
この署名証明をもって、印鑑の代わりにサインのみで遺産分割協議書が作成できます。
②在留証明書
不動産を相続し、相続登記を行う場合など、相続手続において相続人の住民票の写しが必要になることがあります。
こちらも、日本国籍を有する相続人であれば、現地に所在する日本の在外公館にて「在留証明書」を発行してもらうことができるので、それをもって住民票写しの代わりとなります。
また、現在外国籍であっても、もともと日本国籍を有していたのであれば、
既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。(外務省HPより引用)
とあります。条件は証明を受けようとする在外公館によって異なりますので、直接問い合わせが必要です。
③宣誓供述書
海外在住の相続人が日本国籍であれば、上記の署名証明書と在留証明書でほぼ手続は完遂できます。
しかし、相続人が外国籍の場合、そもそもその国に日本のような戸籍制度がなく、相続人であることを証明する書類が不足することもあります。
そうなると、その人物が相続人であること、署名が本人のものであること等、相続のために必要な事実を公証人の前で宣誓し、署名をして「宣誓供述書」を作成することになります。
この書面は現地で作成されるため、その国の公用語で記されますが、日本国内での相続手続に使用する際は日本語に翻訳したものも併せて必要です(訳文は誰でも行うことができます)。
ここまでに挙げた書類は原則としてすべて本人が申請し、取得する必要があります。
予め必要なものを全て確認し、現地にいる相続人本人に不足なく準備してもらわなければなりません。
④台湾在住(相続人が日本国籍)の場合
台湾や韓国には、日本と同じく印鑑証明書制度があります。
現地で印鑑証明書を取得し、訳文をつければ相続登記や金融機関等で手続可能です。
台湾独自の注意点
日本政府は台湾を正式な国家として承認しておりません。そのため、台湾発行の印鑑証明書がそのまま使用できるか。別途認証手続きが必要とならないか問題となります。
詳細は省略しますが、以前は、台湾で2段階の認証、さらに日本で認証といった、3ステップの認証手続が必要とされていました。
しかし、認証手続は時間と費用の負担が大きいため、現在では多くの金融機関や法務局(登記研究 第804号2月号 平成27年3月24日付公式見解あり)において、認証手続なしで手続できるようになっています(ただし、必ず事前に手続機関にご確認ください)。
まとめ
海外の相続人がいる場合の手続きについて解説しましたが、細かい点は国によって異なる部分もあり、やはり煩雑な部分が多くなります。
こういった事例にも経験豊富な司法書士であれば、海外にいらっしゃる方への連絡も大部分を代わりに行うことが可能です。
煩雑な手続きについてもほぼ任せてしまうことができますので、まずは当事務所(市川市・船橋市・習志野市のLEGALMOT司法書士事務所。千葉・津田沼相続相談室)へぜひ一度ご相談ください。
